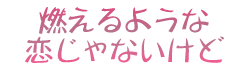 |
今日は昨日の続きで、明日は今日の続きになるのだと信じて疑わなかった。
だから、偶然見ていたニュースで知っている名前が出てきても、同姓同名の別人だとしか思えなかった。それくらい、TVで流れる死亡事故報道は、自分たちにとってどこか遠い世界の出来事で、縁のないものだったからだ。
だから、偶然見ていたニュースで知っている名前が出てきても、同姓同名の別人だとしか思えなかった。それくらい、TVで流れる死亡事故報道は、自分たちにとってどこか遠い世界の出来事で、縁のないものだったからだ。
「ねぇ、なんでいつも光だけ睨んでるの?」
咎めるでもなく、心の底から不思議そうな口調に、赤石修は太い眉を僅かに寄せた。
「目つきが悪いだけだ」
「そうかなぁ」
納得できない様子で、月島若葉は、水着を入れたバックを小脇に抱えた。
「赤石くん、光を見る時だけこーんなになってない?」
若葉は両手の人差し指を立てると、両方の眦を持ち上げてみせた。その大げさな表情と仕草に、赤石は思わず口元をゆるめた。
「オレはそんなに目、細くないぞ」
つられるように、若葉も小さく笑った。
その笑みにどぎまぎしながら、赤石は取り繕うように店内を覗き込み、店先の時計を指さす。
「おい、そろそろ時間だぞ」
「あ、ホントだ」
赤石の指す場所を一緒に見上げた若葉は、バックを抱え直すと、くるりと背を向けた。
「じゃぁね、赤石くん」
途中で振り返って手を振ると、バス停に向かって駆けだしていく。
赤石は見えなくなるまでそれを見送って、それから手にした箒を再び動かし始めた。
赤石と若葉は、酒屋とバッティングセンターという違いはあったものの、同じ商店街で親が自営業同士だったから、物心付いた頃からの付き合いだった。幼稚園からずっと一緒で、いわゆる幼馴染みというやつだ。家族ぐるみの付き合いから、やがてお互い異性として意識し始めてもおかしくない状況だったが、若葉には、同じ病院で同じ日に生まれて、なおかつご近所同士という、赤石よりももっと親しい幼馴染みがいた。
その名を、樹多村光という。
大柄でがっしりとした赤石に比べて、樹多村は小柄で、ひょろりとしていた。真面目に取り組めば何でも器用にこなすのに、飽きやすくて根気が続かない。しかもちゃっかりしていて、赤石が不機嫌そうに近づくと、さっさと逃げる。
それなのに若葉が絡んでくると、自分の嫌いな犬や上級生が相手でも立ち向かうという一面があった。だから、赤石は樹多村の事はかなり気に喰わなかったが、若葉の為には体を張るという点では、嫌いではなかった。
それに実家が酒屋という客商売柄、察する事に長けてしまった赤石は、樹多村が口ではどんなに素っ気なく返していても、若葉と相思相愛であることに気付いている。
生まれたときから一緒にいる相手には勝てないが、諦めるには近すぎる。それに小学生の頃は恋人同士でも、大人になってもそうだとは限らない。
結果赤石は、若葉が樹多村に愛想を尽かすのを気長に待つことにした。
けれど、光と一緒にいる時の若葉が一番可愛い。
だからあの二人が一緒にいるのを見るのは、嫌いではなかった。
夏休みに入ると、開店前に店先を掃除するのが赤石の日課だった。そして夕方には、店前に停まった軽トラから、酒やジュースの入ったケースの出し入れを手伝う。
小遣い稼ぎという名目もあったが、実のところ、その時間帯に店先に立つと、スイミングスクールに通う若葉と会えるという理由があった。
若葉は店先で赤石を見つけると、二言三言交わしていく。それが何よりも嬉しく、そして密かな楽しみで、夏休みや冬休み、春休み中はずっと、雨の日以外は毎日続けた。
二、三年も続けるともはや定番となり、通りかかった時に赤石がいればバスにまだ間に合う時間、と若葉も認識するようになっている。若葉の役に立つのが嬉しくて、明石は毎朝、時間きっちりに店先に立ち、掃除を始めていた。
店先を掃いていると、若葉だけでなく、クラスメイトの女子に出会うこともある。けれど、大きい上に顔が怖いらしく、女子には敬遠されがちだった。
「お前はオレが怖くないのか?」
思い切って、若葉そう訊ねたことがある。
「どうして?」
若葉は、小首を傾げた。
「優しいじゃない、赤石くん」
「そうか?」
「気に喰わないからって、理由もなく乱暴したりしないでしょ?」
それがリトルリーグのことを指しているのだと気付いて、赤石は顔を曇らせた。
赤石は、サッカーよりも野球が好きだった。若葉の家がバッティングセンターというのもあるだろうが、おそらくは高校野球やプロ野球が好きな父親の影響だろう。
小学校の野球部に入り、めきめきと腕を上げると、地元のリトルリーグにスカウトされた。勧められるまま入り、ピッチャーとして将来を有望視されたが、いざ入ってみると、野球そのものよりも人間関係でごちゃごちゃしていて、練習よりもそちらで疲れるようになった。
遠征時には、親が交代で子供たちの送迎を担当しないといけないとか、試合にはちゃんと最後まで応援席にいないといけないとか、よく分からない保護者同士のルールがあるらしい。それらは、酒屋を営む赤石の両親にはかなりの負担で、仕事で満足に関わることも出来ない。「そんな家の子がなんでうちの子を差し置いてレギュラーなんだ」と、親たちが批判しているのを耳にしたこともある。
親がそんな調子だから当然子供の方にも悪影響が出てくるわけで、なにもかもが面倒になった赤石は、両親の悪口を言って喧嘩をふっかけてきたライバルを殴って、さくっと辞めてしまった。
けれど一連の出来事で、野球が嫌いになったわけではない。
「赤石くんも、たまにはウチに打ちにおいでよ」
笑顔で誘う若葉に、赤石は眉を寄せた。そして少し思案して、顔を上げる。
「小遣い貰ったら、考えとく」
そして「そろそろ時間だぞ」と時計を指すと、若葉は慌てて身を翻して、駆けだした。
その日もいつもと変わらず、朝から陽射しが眩しかった。直接肌を刺してくるように強く、熱気が体にまとわりついてくる。
赤石は右手をかざして、青い空を見上げた。
陽が昇りきっていないのにこの調子では、日中はどうなるのだろうか。
「赤石くん、おはよー!」
いつになく上機嫌に片手を振り回し、若葉が駆け寄ってきた。いつもと違い、野球帽を被ってリュックを背負っている。今日からスイミングスクールのキャンプに出かけると言っていたのを思い出
し、赤石は一人合点した。
帽子のせいか、若葉の少し長めの髪が左右に広がって、いつもより可愛い。赤石は頬が上気するのを感じながら、いつも通り軽く片手を挙げて、挨拶を交わした。
「今日ね、すっごくいい夢を見たの」
若葉は身振りを交えて、弾んだ声で話を始めた。
「光がピッチャーで、赤石くんがキャッチャーなの。舞台は超満員の甲子園!」
「まて、月島」
赤石は手を止めて、赤面しながらも若葉を見据えた。
「俺はピッチャーだったんだぞ?」
「うん、知ってる」
「じゃあ、何でキャッチャーになってるんだ?」
「さぁ?」
だって夢だもん、と若葉は苦笑した。
「でもね、キャッチャーの赤石君、カッコ良かったんだよ!」
光がフォアボールで出塁させたランナーを、牽制で刺しまくっていたらしい。
「赤石君は肩強いし、頭いいからキャッチャー向きだと思うんだけどなぁ」
「俺が、頭いい?」
予想外の言葉に、赤石は訊ね返した。
「だって、体育や球技大会でサッカーとかドッヂボールしたら、大抵赤石君がいるチームが勝つじゃない」
「そうか?」
若葉の言葉に、赤石は首を傾げた。
「あれって、ちゃんと作戦たててるんでしょ?」
しかし実際、作戦という程のものでもない。皆がボールの方に集まるから、それを分散し、役割分担を指示した程度でしかない。そう説明すると、若葉は「それでもすごいよ」と笑った。
「あのね、赤石くん」
若葉は両手を後ろで組むと、改まったように赤石に向き直った。
「また野球する気分になったら、光に野球を教えてくれない?」
意外な申し出に、赤石は返事に窮した。
「光、きっといいピッチャーになると思うの」
赤石は、一度だけ光と野球をしたことがある。その時に光は、赤石が本気で投げた球を、ホームランとして盛大に打ち返した。
そして別の日に、ピッチャーとして投げている光を見かけた。
フォームは見よう見まねだったが、コントロールは悪くないし、本気を出したらそれなりのスピードを出せてはいる。しかし、飽きっぽい光が、果たして厳しい練習をしたがるだろうか。
そう指摘すると、青葉は「青葉の練習メニューを渡して、毎日続けるように言っているから大丈夫!」と、妙に自信満々に、ガッツポーズをしてみせた。
「だからお願いね、赤石くん」
「あ、あぁ」
若葉の勢いに押されて、つい頷いてしまう。
そしていつものように店先の時計を確認して、赤石は「あ」と小さく声を挙げた。
背後から「どうしたの?」と若葉が声をかけてくる。振り返ると、真っ直ぐに自分を見上げる瞳とぶつかった。
「今度の夏祭り、手伝いで屋台にいるから」
僅かに視線をずらし、頬をかきながら言葉を続ける。
「どの辺り?」
「狛犬の近くの、ラムネ屋」
「じゃぁ、光と一緒に買いに行くね」
満面の笑みを浮かべて頷くと、若葉はきびすを返した。
「じゃぁ、またね」
そしてトコトコと駆け出したが、不意に立ち止まって、くるりと振り返った。
「赤石くんのキャッチャー姿、とってもカッコ良かったんだから」
そう言って大きく両手を振ると、若葉は正面に向き直って、今度こそ駆け出していく。
赤石は小さく片手を振って、その後ろ姿が見えなくなるまで見送った。足取り軽く店先の掃除を再開し、鼻歌混じりで両手を動かしていく。
帰ってきたら、キャンプでの話を聞かせてくれるのだろう。けれどそれよりも先に、夏祭りで会うに違いない。
はやく明後日にならないかなァと、赤石は願った。